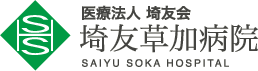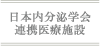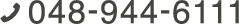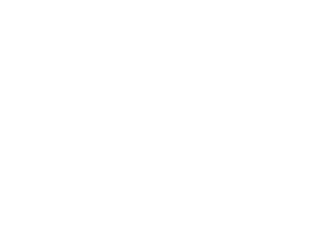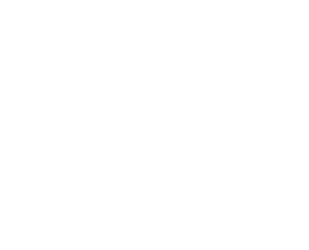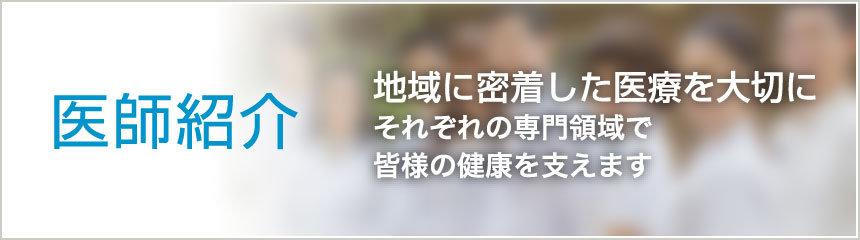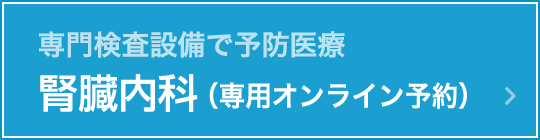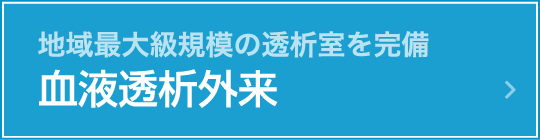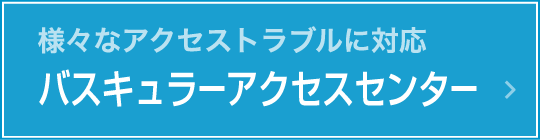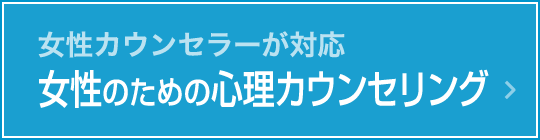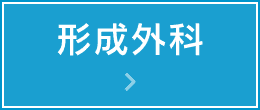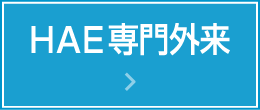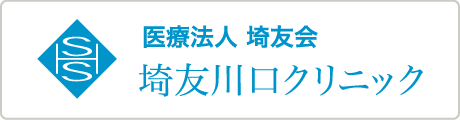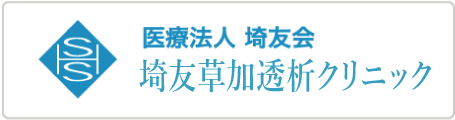生理検査概要
ホルター心電図検査
心臓は寝ている間も休みなく動いています。通常の心電図は短い時間しか記録しませんが、ホルター心電図は24時間記録し心電図の変化を見ることが出来ます。
動脈硬化検査
手足の血圧と心電図・心音を同時に測定し、PWV検査そしてABI検査を順次実施します。PWV検査は脈波伝播速度のことで、心臓の拍動が動脈を通じて手や足に届く速度を測定します。動脈硬化が進展すると弾力がなくなり、脈波が伝達する速度が早くなります。ABI検査は足関節上腕血圧比のことで、脚の血管の狭窄や閉塞の程度を調べます。また、この二つの検査データから大まかな血管年齢と動脈硬化の指標となるCAVI値を算出します。
皮膚灌流圧検査(SPP検査 下肢虚血重症度評価の検査)
この検査は皮膚レベルの毛細血管に、血流がどの程度流れているかを調べる検査です。血管内狭窄及び閉鎖が原因の下肢虚血の重症度評価をするうえで、有益な検査です。任意の血流を調べたい部位にレーザーセンサーと血圧計のカフを巻いて調べます。
脳波検査
人間の脳は考えている時だけではなく、眠っている時にも活動しています。その活動に伴って非常に微弱な電流を流し続けており、その脳細胞の電気的変化を頭皮につけた電極を通して記録し、脳神経の活動を調べる検査です。
肺機能検査
肺は酸素と二酸化炭素(炭酸ガス)の交換を行う最も重要な臓器です。安静及び努力呼吸時の呼吸カーブを記録し、肺の呼吸レベルと肺内空気の容積を関係づけた各排気量分画(肺活量・予備吸気量・1回換気量・予備呼気量・残気量など)や、努力肺活量、呼出開始後1秒間に呼出される1秒量などを測定する検査で、肺の病気の診断、重症度、肺年齢などを調べるのに役立ち治療効果の測定にも使われます。
聴力検査
オージオメーターという機器を使用して、労働安全衛生法や学校保健法などで規定される聴力検査を実施しています。
検体検査概要
生化学検査
血液は人のあらゆる組織を循環して細胞に栄養分を運ぶと同時に、老廃物を受け取っているため、常に全身の健康状態を反映しています。血液は分離すると液状成分の血清と有形成分の赤血球などに分かれます。生化学検査は主としてこの血清成分を使用し、自動分析装置を用いて科学的に分析し、健康状態や病気の診断、治療効果の判定に役立つ検査です。
また、移転に伴い最新の自動分析装置を導入し、従来の機器に比べ検体量の低減・試薬料の低減を実現しました。
また、移転に伴い最新の自動分析装置を導入し、従来の機器に比べ検体量の低減・試薬料の低減を実現しました。
グリコヘモグロビンA1C検査(HbA1c)
血液有形成分の赤血球中にあるヘモグロビンという物質と、ブドウ糖が結合した物質がグリコヘモグロビン(HbA1c)です。一度生成すると極めて安定した物質となり、赤血球寿命が尽きるまで血液中に存在します。そのため過去1ヶ月から2ヵ月前の血糖の状態がわかり、糖尿病治療の重要な検査となっています。
尿検査
尿中には様々な物質が存在し臨床的に重要な情報を与えてくれます。タンパク質やブドウ糖や血液成分などです。当検査科では全自動尿分析装置を導入し、迅速かつ正確にデータを提供しています。
また、尿中にはタンパク質や糖質の他、泌尿器系を構成する細胞成分や血液成分などが排泄されます。これらの細胞成分は技師が顕微鏡を使用し鑑別をしています。
また、尿中にはタンパク質や糖質の他、泌尿器系を構成する細胞成分や血液成分などが排泄されます。これらの細胞成分は技師が顕微鏡を使用し鑑別をしています。
血液ガス分析検査
血液中に含まれる酸素や二酸化炭素の量やPHを測定し、呼吸や抹消でのガス交換、酸塩基平衡などを調べる検査です。
その他の院内検査
・血液凝固検査 ・輸血検査 ・便潜血検査
・アンモニア測定検査 ・インフルエンザ検査
・アンモニア測定検査 ・インフルエンザ検査
診療時間
◆平 日 ◆土曜日 ◆休診日 発熱、咳などの呼吸器症状がある方は、来院前に一度お電話でご連絡ください。TEL:048-944-6111(代表)
【午前】9:00~12:00
(窓口受付時間 8:00~11:45)
【午後】14:30~17:30
(窓口受付時間 12:00~17:15)
※電話対応時間 8:30 ~ 17:30
【午前】9:00~12:00/午後休診
(窓口受付時間 8:00~11:45)
※電話対応時間 8:30 ~ 12:30
※診療科により受付時間、診療時間が異なります。詳しくは外来担当医表をご確認ください。
日曜・祝祭日・年末年始
その他 特診日